死が許されない社会。
自ら死ぬことも許されていない。
この国は政府によって
すべての死が管理されている。
苦しみ悶え涙して叫んでも、
縛り付けられ生かし続けられる。
そんな世界をなんて呼ぶか知ってるか――?
「地獄って呼ぶんだよ」
救済としての死を目指して戦う人々の群像劇
玖珂 悠斗
くが ゆうと
高校2年生 17歳
保護レベル 3
夕月 梅乃
ゆうづき うめの
高校3年生 18歳
保護レベル 3
鎺 宗一朗
はばき そういちろう
医師 34歳
保護レベル ?
死が許されない社会。
自ら死ぬことも許されていない。
この国は政府によって
すべての死が管理されている。
苦しみ悶え涙して叫んでも、
縛り付けられ生かし続けられる。
そんな世界をなんて呼ぶか知ってるか――?
救済としての死を目指して戦う人々の群像劇
くが ゆうと
高校2年生 17歳
保護レベル 3
ゆうづき うめの
高校3年生 18歳
保護レベル 3
はばき そういちろう
医師 34歳
保護レベル ?
若年層(目安として40歳未満)の自己殺人(通称「自殺」)を禁止および厳罰化し、また病気や怪我を無条件で救済する制度を指す。未婚者は無条件、既婚者は子供を3人以上もうけていない場合に適用され、将来の生産力に応じてレベルが設定されている。仮に自殺が成功してしまった場合、遺族に対して罰則が科される。
発達した医学と科学技術により不治と呼べるような病は激減し、病気の進行を遅らせるのではなくほぼ停止させることが可能になっている。外科的治療も著しい進歩を遂げ、人工臓器の移植や臨死からの蘇生までできるようになった。そしていつしか尊厳という言葉はなくなり、延命治療こそが医学の求める道と位置づけられている。
自殺が日本人の死因の多くを占めるようになり、生産人口が著しく減少して国力が低下した社会。人道的観点から死刑制度が完全廃止され生かされ続ける罪人。その生活を税金でまかない、罪なき人たちは税金を払うために自殺の原因を作ってまで働く。増える自殺。減らない件数。そして経済損失。1人あたりの金額を冷たく算出し、数万人という数字の裏側にある感情や事実には目を向けない。発展した医学を礎にして、やがて政府は自殺を禁じる法案を強硬可決し履行した……
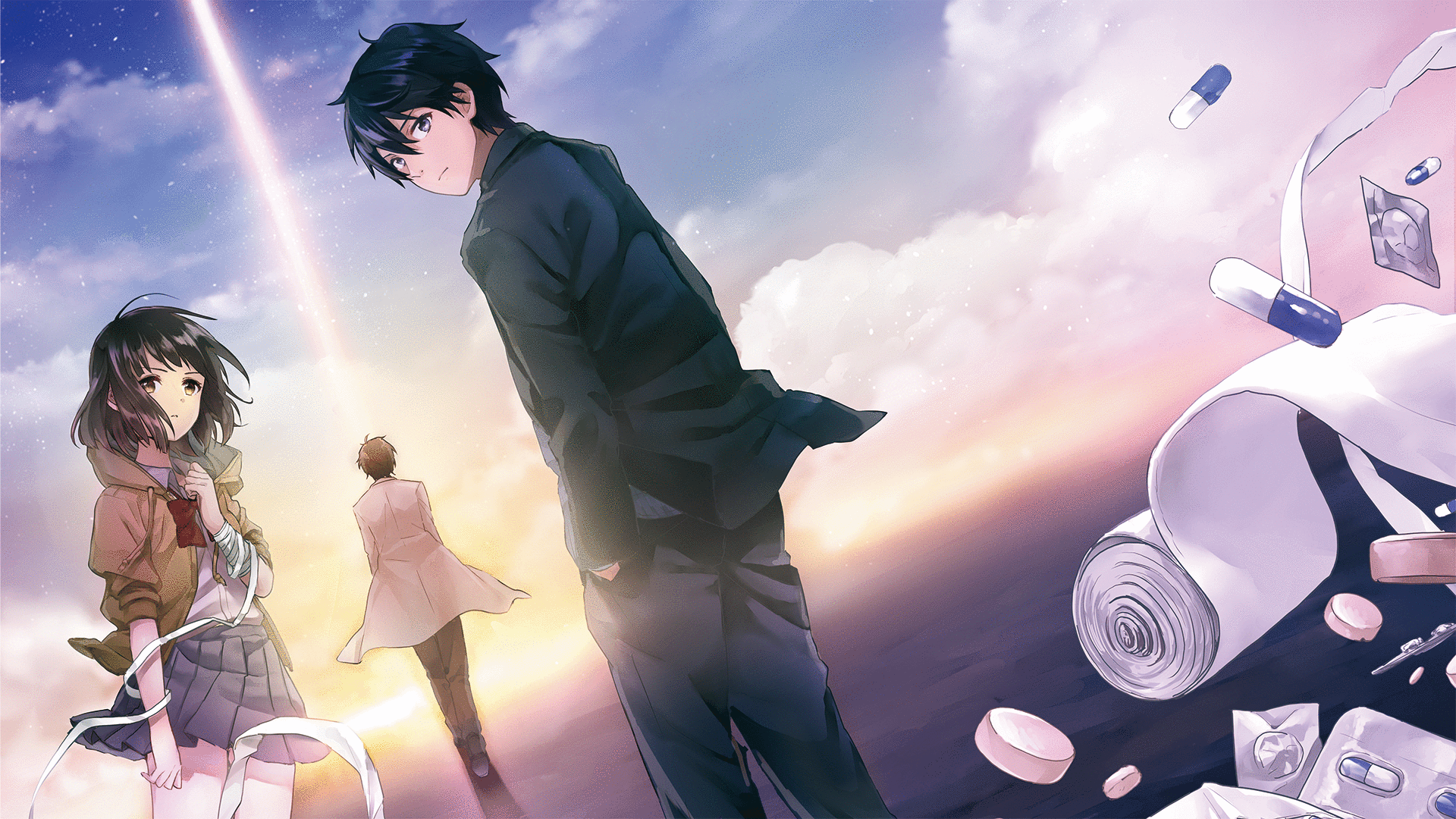
今にも崩れ落ちそうなほど頼りないフェンスによじ登ると、僕はその向こう側へとよろけながら着地した。裾に付いた土埃もそのままに、ふらつきながらもそっと立ち上がる。フェンスの「こちら」側はほんの数十センチの細い世界で、僕は彼岸へと足を踏み入れたような感覚に陥った。見上げれば朝焼けというにはまだ足りない薄明の空に、適当に千切って放り投げたような雲が流れてきた。天頂に淡く見える春の星と半分の月に追われ逃げ出す冬の星座が、西の空で弱々しく揺らいでいる。広大な宇宙のほんの片隅で数十億年も前から飽きることなく自転を続ける地球は、今日も変わることなく夜を見送り朝を迎える。普遍的な時間の中で僕の存在など砂粒の何億分の一にすら足らないのだろう。
僕は自分が今からしようとしていることについて、もう一度思いをめぐらせた。何が正しくて何が間違っているのか。認識している世界の早さと自らの歩みとの乖離。昨日も今日も明日も生きていて、日常を送ることが当たり前だという周りからの無言の圧力。ここから一歩足を踏み出すことが、決して悲観的な感情だけで構成されているのではないこと。それはもっと前向きで希望に満ち溢れていて、ちょうど今朝日が昇ってくる時のような輝きを持っているということ。
少しずつ薬が脳に浸透し、自分と世界の位相がゆらりと変化する。過剰すぎる程に濃度を増した薬は僕のシナプスへと潜り込み、受容体のイオンバランスを崩して深い酔いへと突き落とす。抑制された神経活動は感覚を鈍らせて僕という形そのものをどんどん破壊していく。外殻を破り流出を始めた僕は世界へと溶解し、この世界の感覚そのものになった。風、音、光。そのすべての情報が超感覚的知覚を通したかのように僕の中へと流れ込み、それでいて膜が張ったようにくぐもっている感覚器官で輪郭が曖昧になり、それが世界のものなのか、僕の内部で起きていることなのかを判断することができない。意思は自我から遊離して、薄く淡い影に溶け込んでいった。
水分を吸ってべちゃりと重く張り付いたブレザーは脱ぐだけでもひと苦労で、袖から腕を引き抜きそのまま脱衣所の床に放り捨てると、濡れ雑巾のように不快な音を立ててへたり込みました。濡れ鼠の体で這うようにして浴室に入った私は蛇口を雑にひねり、勢いよくお湯を吐き出し始めたシャワーを湯船の中に投げ入れました。それは水圧でしばらく踊った後、やがて噴水のように熱いお湯を吹き上げながら上を向いて止まりました。
しばしの間、遠く聞こえる雨粒とお湯の流れる音に耳をかたむけていると、ようやく凍えた身体が少しずつ芯を取り戻してゆきます。手足の先がじんと痒くなり、とくんとくんと脈打つ心臓が送り出す血液が、末端の毛細血管に届くのを感じました。しばらくして湯気の充満する中、私はワイシャツの長い袖をめくり、腕を出して手のひらを握ったり開いたり。脳から発する微弱な電気信号は一瞬で神経を走り、寸分の狂いもなく見えない糸のように私を制御しています。
そうだ。いいことを思い付きました。いいえ、正確に言うならば思い付いたのはいつだったか覚えていないくらい前だったと思います。ですが無数にある要因のひとつひとつが欠けていて、今まで実行に移すことができなかった、いいこと、です。それはとても退廃的で官能を刺激する行為。誰にも知られることなく行われる、私が私でいるための儀式。十八歳になった今日、その儀式を実行するのにこれほどふさわしい日は他にありません。
考えてみてください。すごく簡単なことです。想像してみてください。ぞくぞくしてしまいます。私を無自覚に操り表を演じる糸を断ち切るのです。傀儡となった私を囚われの身から解放するのです。
肌にそっと刃先を押し当てて、なぞるように、線を引くように。ちくりとした痛みは赤い線となって肌に焼き付きました。
そう。次はもっと深く。引き裂くように、抉るように。流れ落ちた滴は、酸素に触れて赤黒く狂い咲くことでしょう。
この建物はおおよそ喧噪という言葉そのもので構成されていた。そして科学技術の粋を結集して揃えられた設備、同時にある種の静謐さを湛えた空間は、冷気にも似た非情さをも併せ持っている。ここが僕の家であり、職場でもある。自らを幽閉しているかのごとく僕はこの建物から基本的に外へは出ない。以前「鎺先生、そんな生活をしていては頭がおかしくなってしまうのではないですか」と訊かれたことがある。そうではない。順序が逆なのだ。思考がズレているからこそ、こんな世界で生きているのだ。病院と言えば絶えず人が出入りし、生と死が混ざり合う此岸と彼岸の境目のように思われるかもしれない。ところがこの救急病院に限れば、そんなことはまったくない。この世界において、死からは一番遠い場所である。
生と死は有史以来普遍的に人類を悩ませ、そして永劫のテーマとして様々な分野に根底から影響を与え、それそのものがひとつの哲学として捉えられてきた。産み落とされた命は死を可能な限り回避しようとし、それは人に限らずすべての生きとし生けるものに対して言えることで、実に自然なことでまさに本能だ。
しかし医学と呼ぶに値するものを発展させたのはやはり人間だけだった。それは人にだけ与えられし英知で、死という不可避な現象から逃れるためのイレギュラーな因子でもあった。この世界すべてを神が創造したというなら、医学と科学技術により死が先延ばしにされ生にしがみつく人間たちは一体どのように見えるのだろうか。知恵は迫り来る死を退け、苦痛と待ち受ける苦難に立ち向かう。なんと美しく脆弱で狂おしいのだろう。そして虫けらのように藻掻き苦しみながら死に向かって生きてゆく。いつしか死の理そのものをゆがめてしまうほどに医学は発展し、倫理は禁忌へと手を伸ばした。それは神への冒涜なのか、懸命に生きようとする健気な存在として写るのか。